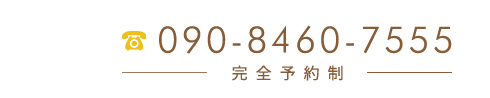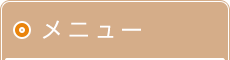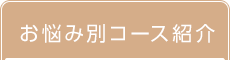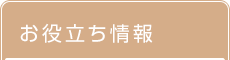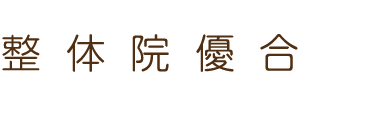本当に多くの方が悩まれている肩こり・首こりですが、
男性よりも女性の方が悩まれている方が多いです。
これは筋肉量の問題があると思っています。
頭の重さ・大きさは男女でそこまで大きな差はないですが、
首肩周りの筋肉量は男性の方がかなり多いです。
つまり、同じ重さの物をより少ない筋肉で支えいている女性、、、。
その筋肉達が硬くなってしまい張り感やこりとなる、、、。
とはいえ、男性でも肩こりの方はいますし、
女性で肩こりのない方もいます。
どこが違うのでしょうか?
この違いが予防法になるのではないでしょうか。
肩こり・首こりの予防法
以下に一般的な予防法を紹介していきます。
✅ 定期的なストレッチ: 首や肩をゆっくり回したり、肩甲骨周りをほぐすストレッチを行う。
✅ 適度な運動: ウォーキングや軽いジョギングなどで血流を改善する。また肩周りの筋肉の強化をすることにより、頭の重さによる肩周りの筋肉が過緊張にならないようにする。
✅ 水分摂取: 1日に1.5〜2リットルの水を飲むことで血行を促進。
✅ 質の良い睡眠: 睡眠中に筋肉が修復されるため、寝具や枕の高さを調整して快適な睡眠環境を整える。
✅ 入浴: 入浴時にちょっと低めのお湯でゆっくりと入り、血流を改善する。
✅ ストレス管理: 深呼吸や瞑想、趣味の時間を確保して精神的な緊張を和らげる。
✅ 姿勢:前かがみの姿勢や猫背の姿勢にならないように注意する。
知らなかった内容もあるかもしれませんが、
これらが予防法として良く知られています。
これらの実施していても
肩こりや首こりが予防できない、、、。
辛さが変わらない、、、。
という方は、以下のことが原因なのかもしれません。
バランスが崩れている
前項目で挙げた予防法を実施しても肩こり・首こりが改善しない方は、
以下の原因が考えられます。
- 上半身のお腹側と背中側のバランスが崩れている
- 下半身のバランスが崩れている
- 体幹が弱っている
この3つのことが考えられます。
上半身のお腹側と背中側のバランスが崩れている
上半身のお腹側と背中側のバランスが崩れている、、、。
ちょっとわかりにくいかもしれません。
猫背や巻き肩がの人は、
肩こりや首こりになりやすいと聞いたことがあるかと思います。
猫背や巻き肩の方は、
お腹側(前胸部や腹部)の筋肉が硬くなって縮んでしまい、
上半身を丸くする様なバランスになっています。
反対の背中側の筋肉(菱形筋や僧帽筋下部)は上半身が丸くなっている為に、
常に引っ張られてしまい、筋肉は引っ張られたら引っ張り返すので、
筋肉が疲労で筋力が十分に発揮できていない状態で弱くなっています。
そこで必要なのが、
お腹側の筋肉の硬さを取ると同時に、
背中側の筋肉の強化です。
その結果として上半身のバランスが整い、
肩こりや首こりが改善していきます。
下半身のバランスが崩れている
下半身のバランスが崩れている。
例えば、右の股関節と左の股関節の動く範囲が違う。
足首の動きが左右で違っていたり、
片方の足首の捻挫をする・したことがあり、
その回数が多かったり靭帯の損傷をしたことがある、、、。
などです。
例えばですが、
ビルを建てる時に地盤が左半分はきれいに平らだが、
右半分の地盤は凸凹している。
その上に建てたビルはどこかの階で歪みが出てきてしまいます。
つまり、足元がバランスが悪いと上半身に歪みが出る。
その結果、歪みの影響で肩・首周囲の筋肉が硬くなる、、、。
この場合は、下半身のバランスがどのように崩れているかを確認し、
その結果に応じた施術等をしていかなくてはなりません。
体幹が弱っている
身体の上半身と下半身を繋ぐ身体の大事なところ、体幹。
これが弱いと身体が安定しません。
身体の中心が安定しないと余分な力を使いながら身体を動かします。
例えば、歩く時にアスファルトの上と砂浜の上。
どちらが歩きやすいですか?疲れないですか?
アスファルトの上ですよね。
アスファルトが安定しているので余計な力を使わないので疲れない。
体幹が弱いと身体が安定しないので、
余分な力を使いながら動くこととなる。
その結果として筋肉が硬くなる。
身体の中心から遠い肩や首周囲の筋肉は、
不安定の影響を強く受けてより硬くなり肩こり・首こりとなる。
この様な方は体幹の筋力強化が必要です。
硬い肩や首周囲の筋肉をマッサージやストレッチで緩めても、
体幹を鍛えないと硬くなってきます。
その時は良いけど、日数が経つと硬さが戻ってきてしまう、、、。
体幹を鍛えるために腹筋などを始めようとした時の注意点です。
鍛えるのは腹筋ではなく体幹筋(深層筋やインナーマッスル)です。
体幹筋を鍛えることにより身体の安定性が上がり、
肩こり・首こりが改善していきます。
まとめ
肩こり・首こりは、
原因がその方によって違います。
その違いを理解したうえで、
改善のため・予防のために行うことがはっきりしてきます。
ただやみくもの何かを行うのではなく、
自分にあった内容を行ってみてください。